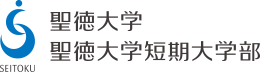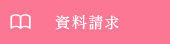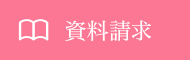日本語・日本文学コース口頭試問
25.03.03
日本語・日本文学コースの口頭試問は、1月20日、22日の2日間に分けて行われました。
卒業論文を提出した4年生の皆さんが1人ずつ試問室に入り、まず自分の卒業論文についてのまとめをしたあと、コースの5人の先生方から質問や指摘を受け、答えていくという形式になっています。
学生の皆さんにとっては、卒業までの最後の難関、ドキドキの瞬間のようです。

今年度の卒業論文も幅広いラインナップとなり、粒ぞろいの研究が揃いました。
まず、日本語学の分野では、メイク用語の専門家アクセント(専門家がその語を発音する際にアクセントが平坦化する現象)、ディズニープリンセスの女性語(「~だわ」「~かしら」など)の出現といった、近年注目されている言語学的現象を調査した労作が目を引きました。
また、混種語「外来語+和語+する」(「プロ入りする」「マニア受けする」など)を形態論の視点で論じたものなど、丁寧な検証がなされた論文がありました。
古典文学では、『今昔物語』と『伽婢子』に登場する「人ならざる者」に注目した力作、狐が人間の女性に化けて姫君に尽くす『玉水物語』、BL作品との関連で現在注目を集める『男色大鑑』など、学生を魅了する作品をとりあげる卒業論文がみられました。
そのほか、作品横断的に考察する研究もあり、「扇」あるいは「文付枝』といった平安期ならではの小道具に着目するもの、『とりかへばや物語』の異性装を中心に、平安時代においては男性も女性もさまざまな色の着物を身につけていたことを論じた興味深い研究もありました。
近現代文学では、ここ数年、文豪・谷崎潤一郎の人気作、現在進行形で活躍する小川洋子の作品をとりあげる研究が多いのが特徴といえますが、今年度は小川国夫の中編小説『試みの岸』を丁寧に読み解いた労作が目を引きました。
また、沖縄県の八重山方言のアクセントの追跡調査を行った研究、青森の「ねぶた」でとりあげられる『平家物語』の題材を考察した研究など、自らの出身地をテーマにした卒業研究もありました。
日本の言葉や文化がどのように受け継がれ、変化していくのかを明らかにした、大きな意義のある感動的な研究といっていいでしょう。
日本語・日本文学コースの卒業論文は、3年次からテーマを定め、1年以上にわたって、そのテーマに向き合うことがほとんどです。中には2年生の専門ゼミ入門の頃からずっと調査を続けたという人も。
口頭試問の締めくくりは、1人1人がこの4年間と卒業論文について振り返りました。
卒業論文の執筆は時に孤独な作業でもありますが、ゼミの仲間と励まし合ったり、先生方と相談したりしながら乗り越えていったことがうかがえます。
この聖徳大学文学部での経験を生かし、4年生の皆さんが、これから先の自分の人生を切り拓いていくことを期待しています。