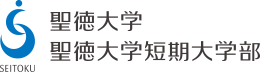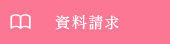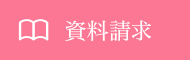RE科目「文豪を訪ねてⅠ」報告①
25.05.28
「日本一楽しく学ぶ」をコンセプトに開設された聖徳大学文学部の参加型体験授業「RE科目」(REとは、Reality Experience:人生におけるとても貴重な本質的体験という意味)のご紹介です。

RE科目「文豪を訪ねてⅠ」ではこのほど、森鷗外と夏目漱石に迫ろうと、1回目の学外授業を実施しました。まず訪れたのは東京都文京区千駄木の区立森鷗外記念館です。

記念館は鷗外の旧居(観潮楼)跡に建っています。鷗外は1892年(明治25年)から、60歳で亡くなる1922年(大正11年)まで、この地で暮らしていました。鷗外が見た風景を追体験し、鷗外が歩いた道をたどり、鷗外の思索の跡を追いかけたくなるような建物です。


館内ではちょうど、特別展「本を捧ぐ 鷗外と献呈本」が開催中でした。鷗外の居宅には、鷗外夫人が「宅では本がたんすを追い出します」とこぼすほど、本があふれていたようです。ジャンルも、文学や医学はもちろん、哲学、歴史、自然科学、美術など、多岐にわたっていました。鷗外の並はずれた学識はこの読書量に支えられていたものでした。


会場には文学者などから贈られた本、鷗外が他の文学者に贈った本が一堂に展示されていました。北原白秋や石川啄木など、鷗外より若い文学者から献呈された本には、鷗外への尊敬の念がうかがえます。一方、与謝野晶子へ鷗外が贈った本からは、鷗外が彼女を文学的に信頼していたのではないかと感じさせます。
特に目をひいたのは、夏目漱石との交流でした。漱石から鷗外へ贈られた漱石の長編小説『門』と『彼岸過迄(ひがんすぎまで)』が出品されていました。書簡も合わせて展示され、日本近代文学の双璧を成す2人の文豪のやりとりには心が熱くなりました。
見学をした後、学生たちは「鷗外が5歳から熱心に勉強していたのに驚きました」「当たり前のことなのですが、鷗外が生きていたことを実感しました」「少し大げさかもしれませんが、明治の文豪たちが魂のやりとりをしていたようで、感動しました」と口々に感想を話していました。
次に、歩いて東京大学の本郷キャンパスへ。安田講堂の前で記念写真を撮った後、三四郎池を訪れると、その周辺は静寂が支配していました。夏目漱石『三四郎』の場面を思い浮かべながら、学生たちは友人同士で語り合っていました。元気な学生は池を一周して、文学作品の舞台を楽しんでいました。


【お知らせ】
「聖徳大学文学部Instagram」では、さまざまな1分動画の連載が始まりました。
たくさんの学生の「生の声」が聞ける動画になっています。ぜひブログと合わせてご覧ください!
https://instagram.com/seitoku_bungaku?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==