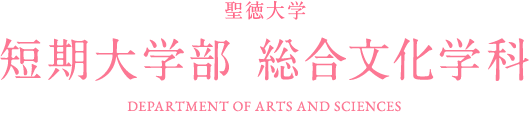(207)江戸の珍談・奇談(27)-1 20220504
22.05.04
その名もズバリ「近世珍談集」という一冊がある。三田村鳶魚編『未刊随筆百種』第12巻に収められた小品であるが、書誌が不明らしい。この叢書自体、鳶魚所蔵の写本に拠ったものであるから、刊本となっていない。また、国立国会図書館のデジタルコレクションにも収載されていないようである。この書に関する鳶魚の解題は、わずかに下記の64字しかない。
僅々三件の話頭ながら、江戸の黄金時代とも思はれたる頃に珍談として、噂の種子となりたる事柄のさまを按じては、世態人情を観察するに宜し、(同書、7ページ)
いつ、誰の著したものか明らかでない。だが、文中に俳諧師歩牛(鵲庵、玉田久左衛門)が筆者に語ったと見える。その歩牛(鵲庵)は、文政10年-1827-に『百合の花』という句集を刊行していた(岡山市燕々文庫目録による)。また、第一話の冒頭に「今年享和元年-1801-」とあるから、享和から文政にかけての話を収録したもので、鳶魚が「江戸の黄金時代」と言った文化・文政時代に相当する。
収載された三編のうち一編は、だれだれの直談と明記してあるし、一編には上記の歩牛の語った実談とあるから、単なる噂話でもなく作り話でもない。まず、第一話「蛙(かわず)の歌詠ぜし事」からその前半を紹介しよう。
大御番頭(おおごばんがしら)堀近江守(直起(なおのり)、越後椎谷藩主)の組に、飯河三郎義従という人がいる。風雅で、和歌の仲間に飯田町の火消屋敷与力である福原左近兵衛という人があった。その妻を甲斐という。夫婦ともに和歌を好んで詠む。享和元年の春、三郎義従が京都在番の帰りに井手の蛙を生きたまま持ち帰り、左近兵衛に土産として渡した。夫婦そろって風雅人でもあり、ことに名にし負う井手の蛙であるから、さても珍しい物だ、何よりの土産だ、と左近兵衛は格別に喜んだ。蛙を愛玩して秘蔵し、飼育しておいたところ、ある夜、女房甲斐の夢に、歌会を催し、友達五六人を集めた。例の井手の蛙を取り出して土産に貰った由を告げたところ、皆驚きながら見て、「昔、能因法師が井手の蛙と長柄の橋の削り屑とを嚢中に収めて首に懸けていたというが、それは蛙の干物だった。これは生きた蛙だ。いやはや珍しい物だ」と言って、それぞれに詠歌が出来た。それを短冊に認め、蛙を入れた箱の上に短冊を重ね置いて、よもやま話に花を咲かせる。皆が帰った後、甲斐が蛙の方を見たところ、蛙が声高らかにこう詠んだ。
立ち出でし井手の川辺の名残をもしばし忘れし水茎の跡
(=出立した京都の井手の川の辺りの名残惜しささえも、しばしの間忘れることができた。
風雅人の詠んだ歌によって。)なんと不思議なことだと思っていると、夢が醒めた。忘れないようにと、直ちに起き直り、燈火の下でこの歌を書き留めて、人々に伝えたという。(同書、223ページ)
文中の「井手の蛙(かわず)」とは、現在の京都府井手町を流れる玉川に鳴く蛙(カジカガエル)のこと。古来歌枕として有名であった。
・かはづ鳴く井手の山吹散りにけり花のさかりにあはましものを(古今・春下・125)
・隠れ沼(ぬ)に忍びわびぬるわが身かな井手のかはづとなりやしなまし(後撰・恋二・606)
蛙が歌を詠むとは、「生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」(『古今和歌集』仮名序)を地で行くような話だが、これは夢の中の話。まだ続きがある。この話を筆者に語った歩牛が、同じ俳諧師梅人(三河田原藩主三宅豊後守康友の御用人平山梅人、享和元年10月歿)に話すと、梅人自身もその蛙を貰ったという。秘蔵して飼育していたが、4月頃までは鳴いたのに、それ以降鳴き声が止んでしまった。夏に至っても鳴かない。ある時屋敷の長屋下を笛売りが通り、色々な虫笛を吹いた中で、ヒグラシ蟬の笛の音を聞いた時、蛙が突然鳴き声を発したのである。その笛を買い求めて、鳴かせようと思う時に吹くと鳴いた。やはり他の蛙とは鳴き声が余程違うと梅人は言っていた。
因みに、平山梅人は、かつて芭蕉の住んだ深川庵に残っていた古い文書を集めて『続深川集』を編み、蕉翁百回忌の報恩に供えたという。(G)