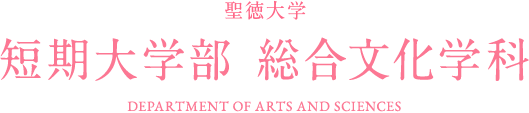(189) 江戸の珍談・奇談(25)-17
19.08.02
「カスタマーハラスメント」という用語を耳にすることが多くなった。店側の過剰サービスが客側の過剰期待を生むことが原因だという。店としては、商売だから顧客を失いたくない。客の方が上という意識がどこにも浸透している。だが、困った客はいつの世にもいて、それに手を焼いてしまう。
博打、飲酒を好み、世に言う「蔵宿師」(旗本から依頼された借金の交渉人)を業としていた男があった。思わぬ金が手に入ると、ある限り花柳に遊び、美食に耽る。金が尽きれば、再び悪事に手を染める。今日は美服・美食に奢るかと思えば、明日は破れた衣服に米もない。
ある年の暮、懐具合が悪く、一人娘が破れた着物のままで年を越す手立てがつかないでいた。既に大晦日である。借金取りが取り立てに来るが、もとより返す当てがあるはずもないから、皆苦り切って引き返す。ほっとしたものの、娘に晴れ着も着せてやれないのはつらい。金二分(=一両の半分)程度の工面をせねばならなくなった。普通の日だってこの人に快く金を貸すような者はない。こんな年末になってどこへ持ちかけようというのか。また、悪事も、人々の心に油断がある時には行えるが、この時期に至っては誰も騙されはしない。わずか二分の金を手に入れるために思い付いたのは、不思議な窮余の一策であった。
程近くにある仕出し料理屋へ行って、大勢の客をもてなすため、三両ばかりの料理をすぐに持って来てくれ、と頼んだ。大きな魚を第一として、塗りの器は大きいのがよい、皿でも台でも、皆大ぶりな物に盛ってよこしてくれ、と言って帰った。間もなく届いたのは、藍染付けの大皿に頭と尻尾がはみ出すくらい大きな鯛の浜焼きが載っている。平皿には、鮪(しび)とヒラメの刺身を敷き並べ、山海の珍味を盛り添えてあった。その他、魚の肉や鳥の肉など見事な品ばかりである。それらが高級な器物に据えられているのはいうまでもない。およそ三両でこれほどの品々が揃うとは、予想外であった。
さて、来客があるとは初めから嘘であるから、どうするのかと思うと、料理はすべて家の前の溝に棄ててしまう。井戸の水で器の汚れを洗い流し、重ねて広い風呂敷に包むと、近くの質屋へ持って行った。黄金二分を借りた帰りに古着屋へ立ち寄り、娘の晴れ着を一着買って帰る。娘も自分もうまく行ったと喜んで年を越した。
年が明けて、器と飲食代を請求する使いが料理屋からやって来る。もう少し食べ残っているから器が空いたら返すと言って使いを帰した。後刻再び来ると、客の所へ送ったから、戻って来たら帰そうと答える。こちらも使わなければならないので、送った先へ取りに行きましょうと使いが言うと、それはそっちだ、いやこっちだと言うのを聞くと、どこも一里も二里も離れた場所であるから、どうにもならない。二・三日過ぎても連絡がないので、怪しいと思って使いが問い詰めると、前と同じ答えで、はっきりしない。さては騙されたか、飲食代はともかく、器の行方だけでも教えてもらって取って帰れ、と主人が使いに言い付けてやると、もうしばらくと言っては返さない。
困り果てたので、こちらから詫びを入れた。「飲食代はいただきません。ただ器だけお返しくださったら、この上ないお慈悲でございます。どちらへお送りになったのですか。それをお教えください」と言うので、男は、「いや、代金は明日にでも取らせるつもりだ。タダ食いはしない。器もその折に返そう」と言う。いよいよ持てあぐねてしまい、ひたすら器の行方を問うと、それなら何屋へ行って取れと言う。何屋とは質屋のことである。「ほら、思ったとおりだ。この器の値段は飲食の代金とは比較にならないから、利息が増さないうちに、早く行って請け出せ」と主人が言うので、使いが行ってみると、わずか二分の質草に利息が付いたままだったので、一安心と受け戻して帰った。〈『反古のうらがき』72~74ページ〉
器の中にあった品々を人にも贈り、自分も食べたら、さぞかしうまかったろうに、こういう人は物惜しみはしないものだ、と鈴木桃野は結んでいる。この男はおよそ品行方正と言えないが、娘思いという点で憎めないところがあったのかもしれない。鈴木は、この話のタイトルを「くるしきいつはりごと」と犯罪扱いしなかったうえ、「これは余がしれる人なれども、其名明し難し」と姓名を明かさなかった。