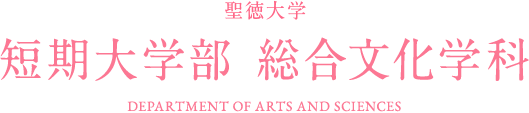(111) 江戸の珍談・奇談(7)-2
14.05.28
石出帯刀という名は、牢屋預りに就いた者が代々襲名するものである。明暦の大火の際、囚人の切り放ち(=解放)を敢行した石出帯刀は、本名を吉深(よしふか)といい、常軒と号する。元和元年(1615)の生まれだから、明暦3年(1657)には42歳の分別盛りであった。
一体、江戸は火事が多い。明暦以後享保5年(1720)までのわずか60年余りの間に、都合6回の大火により、牢屋敷が類焼している(三田村鳶魚『江戸の珍物』160ページ)。その度に囚人の牢払いが行われたのであり、無論、吉深の前例に倣ったものであった。
三田村鳶魚によれば、吉深は中山道嘉門宿(=現在の北千住)に住む石出家の次男佐兵衛と称した人で、それが幕府へ召し出されて牢屋預りとなった。石出の本家は、三田村の執筆した大正2年当時でも北千住で紙屋をしていて、地方随一の旧家だという(同書159ページ)。
だが、吉深の出自には別伝もある。三河の譜代本多某の子として下総香取郡に生まれ、後に江戸小伝馬町の牢屋奉行石出家の2代帯刀義長の養子となる。養父の死後、寛永15年(1638)、牢屋奉行を継いだ(『国学者伝記集成』第1巻)。
吉深は、常軒という号を有するだけあって、風流韻事を解した。連歌を好み、『春雨抄』なる著述もある。寛文7年(1667)52歳で致仕するまでに連歌集、歴史記録文、紀行文、日記などを残し、さらに隠居後、『源氏物語』の注釈を完成している。
この注釈書は、『窺原抄(きげんしょう)』と題された全62巻にも及ぶ大部のもので、延宝7年(1679)から貞享2年(1685)までの6年間を費やした労作である。亡くなったのはその4年後の元禄2年(1689)3月2日であった。
吉深が源氏物語注釈の執筆に取り掛かる6年前に、北村季吟『湖月抄』60巻が成立していた。『湖月抄』はいわゆる旧注(=国学以前の注釈)の最高峰とされる。だが、ほぼ同時代といってよい時期に『湖月抄』に匹敵する規模の注釈書が、牢屋預りであった幕府役人の手で著述されたという事実が大いに興味を惹く。
全巻揃った写本は、東北大学図書館にある。今一つ、国立公文書館に蔵されている13巻本(桐壺から須磨まで)を見ると、端正な筆づかいで記され、誤った箇所には紙片を貼るなど、丁寧な処理を施してある。もしこれが単なる浄書でなく、読解・考察しながらの執筆であったとすると、かなりのハイペースで書いたことは確かだ。
例えば、桐壺を終えたのが延宝7年9月15日であり、帚木上を同年10月5日、帚木下を10月20日には記し終えている。続く夕顔などは80丁(=160ページ)近くある。それを11月4日から12月12日までのわずか1カ月強で仕上げているのだから驚く。1ページ15行と字数が少ないことは問題にならないだろう。
明暦の大火において自らの命を顧みず囚人を解き放ったというだけでも、十分に感銘に値する逸事であるはずだが、後半生において、『源氏物語』の注釈に没頭し完成したというのだから、もはや感服の域を超えた羨むべき人生だといっていい。
だが、残念なことに、『窺原抄』はいまだ活字化されておらず、江湖にその名すら知られていない。吉深が季吟の影響をどこまで受けたかを含め、その評価については、今後の調査研究が俟たれるところである。