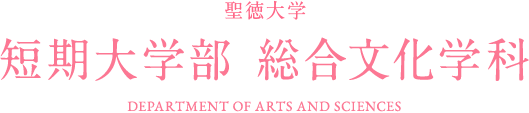(69) 柴五郎の遺文(7)
13.03.13
年が改まるころ、母の実家のある御山に病院が建設され、敵味方を問わず診療が行われた。太一郎もここで手当を受けている。山荘の生活にすっかり慣れ、百姓の姿で土にまみれて過ごす安穏な日々を送っていた五郎少年に転機が訪れる。
明治2年6月、御山病院の傷痍者もおおむね治療を終え、俘虜として東京に護送されることになった。晒し者として江戸に連れてゆかれるくらいなら、この地にとどまって百姓となり、母の墓所を守りたいと、太一郎兄に申し出るが、「辱めを受けたら、江戸でもどこでも斬り死にか、腹掻っさばいて会津魂を見せてくれようぞ、今から気弱になってどうするのだ」と語気激しく叱責されると、うなだれて従うしかなかった。
出発に際し、負傷者には身分に応じて看護人を一人伴うことが認められた。そこで、官軍と交渉して、五郎少年は留吉の名を出願し、許可される。
梅雨時であった。連日雨にけむり、太陽が見えない。負傷し歩行が困難な太一郎兄には板輿が与えられる。蓑笠を着てこの上に坐し、さらに茣蓙(ござ)をかぶって雨を防ぐのである。五郎少年は、徒歩で後を追うが、雨水を含んだ蓆が重くて難渋する。見かねた官軍の監視兵が板輿を徴発してくれた。首から腕を吊った者、両杖に足をひきずる者、荒い息遣いばかり激しく足が運ばないため、次第に列から遠ざかる者、下男に背負われた白髪の老体、まさに「乞食の大名行列」としか思われなかった。
梅雨の明けた、耐え難い蒸し暑さの中、ようやく東京に入る。一ツ橋門内、御搗屋(おつきや)と称する幕府糧食倉庫に到着した時には、疲労が極限に達していた。木造二階建ての広い倉庫で、階下は土間である。漬物置き場らしく、沢庵漬けの匂いが充満し、湿気がはなはだしい。
東京に送られた会津藩士は、音羽の護国寺、小川町の講武所、麻布の幸田邸、御搗屋の四か所であったが、後に芝増上寺が加えられた。すべて「謹慎所」と呼ばれる俘虜収容所であり、監視兵付きである。後に、飯田町火消屋敷跡に会津藩事務所の新設が許され、山川大蔵を総督とし、旧藩の役員並びに有力者を集めて連絡統制に当たることになる。太一郎兄はこの事務所に移り、松島翠庵と名を変え、医者の姿となった。藩士の行動は限られていたため、医者となって自由に他藩の友人・知人を訪ねまわり、会津藩の善後策について助力を求めるためである。
9月27日、祖先の祀りをなすため、南部の地を割いて三万石を賜うという恩命が下った。当初、猪苗代か陸奥の国かについて、意向を訊ねられたが、猪苗代は旧領の一部だから、経済的にも精神的にも受け入れにくいという意見が多く、未知の土地とはいえ、宏大な陸奥に将来を託すほうがよいだろうと議が決し、「徳川慶喜、松平容保以下の罪を免ず」との詔勅が下る。藩士一同感泣して喜んだのだが、五郎少年は疑念を拭い去れなかった。
このことは幼き余にとりて不可解千万なる出来事として脳裡に刻まれたり。罪を免ずとは何事なるぞ、罪は薩長の策士等にあり、彼等を罰して余等を赦免するが当然なりと悲憤やるかたなきも、お家復興を祝いて祝意を表する藩士らの明るき表情に接し、何事も問い質す自信を失えり。〈第一部、51ページ〉
彼の不安は的中した。
慶応3年の時点で、会津藩は旧領30万石、京都守護職などによる増封5万石、第一回職封5万石、第二回職封5万5千石、加うるに、月2千俵、月1万両を賜わっていた。石高に換算すれば、67万9千石の大藩である。そこへ、陸奥の国、旧南部藩の一部3万石に移封された。厳しい措置とはいえ、藩士一同感涙に咽んだものの、新領地は半年雪に覆われた、下北半島の火山灰地である。この痩せた土地では実収7千石しか見込めない。藩士全員を養うことなどとうていできないことを、この時、誰一人知るものはなかった。