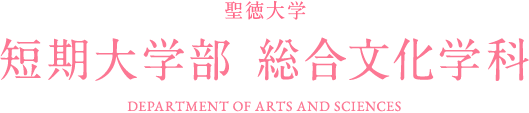(143) 江戸の珍談・奇談(20)
15.10.10
紀伊国屋文左衛門といえば、江戸の比類なき大尽として知らぬ者はない。単なる大金持ちというだけでなく、風流人でもあった。節分の豆撒きに、豆の代わりに金をばらまいたなど、様々な逸話を持つ中で、江戸座の俳諧師神田庵の主が語った、いかにも紀文らしい遊びがある。
昔、紀文が隆盛を極めた頃、ある夏のことだったが、浅草川で船遊びをすると世間に触れ廻した。どんな遊びをするのか見物しようという群集が、当日になると我先に競って船に乗ったため、川面は水の色さえ見分けられないくらい。紀文の船は今来るか今来るかと待っているのに、夕陽が傾く時分になっても、何らそれらしき気配がない。遂にあちらこちら捜し回る船まで現われた。火ともし頃になって、川面のここかしこに盃が流れて来る。それまで酒を飲んで歌を歌っていた船は、どよめきながら川面を見守る。ただ盃が流れ寄ってくれることを待ち、そればかりを争って興じたのだった。これはまさしく紀文のしわざにちがいないと、上流を尋ねようと船を墨田、綾瀬の方へ溯らせ、隈なく探し求めたものの、その夜はまったく紀文の姿を見つけることができなかった。夜が更け、仕方なく皆帰ったという。〈大田南畝『仮名世説』-『日本随筆大成』第2期 2、290ページ〉
その日、紀文は、船遊びに出ると言い触らしておき、自分は家にいて、盃だけを流させたのだった。後に人々が聞き伝えて、その風流を称讃したという。問題の盃は、大した細工も施してない朱塗りの平凡な品であったそうだが、この話を語った神田庵主の家には、紀文の酒盃として収めてあったと大田は紹介する。
上述の豆撒きも同様、金品に群がる人間を見て満足を得ようとする行動に対して、小文の筆者なら眉を顰める。およそ風流とは呼べないであろう。だが、この話ばかりではなく、当時の人々は、紀文の行動に対しておよそ批難めいた言い方をしない。不思議な感覚である。
紀文の姿は拝めなかったものの、隅田川に出た群集は、盃を手に入れた。だが、もし触れ廻らした案内が虚報だったとしたら……。
夏の六月、両国川の夕涼みは、誠に三国一の景色といってよい。今宵は、名にし負う仙台の太守が花火を打ち上げさせると、江戸中に触れ廻している。貴賤すべてが花火を見物しようと、屋形船は勿論、小舟に至るまで借り切って、もはや江戸中に空き船は一艘もないという有様。川は一面に船で埋め尽くされている。ところが、暗くなっても花火の沙汰が一向にない。これはどうしたことだというと、お屋敷に不都合があって、明後日の晩に延期されたというではないか。名残を惜しみながら皆帰って行く。しかし、その当日になっても花火は上がらない。さては騙されたかと、その時になって人々は目を覚ました。騙した張本人は、江戸橋の船持ち上総屋三右衛門という者で、江戸中の船持ち連中に、その夜銭を設けさせてやろうと企んだことだった。〈馬場文耕『当代江都百化物』-同上、394ページ〉
せっかく船まで出して待っていたのに、二回までも肩透かしを食らわされたのでは、腹を立てても当然であろう。だが、それが仙台藩主の嘘ではなく、船持ちに騙されたと判明したところで、当時の人々はどう反応したのか。そこまで書かれていないが、うまいことやられたと、むしろ感心するくらいで、恐らく洒落の一つとして笑って済ませたかもしれない。馬場文耕も「誠ニ能キ化シ様ナリケリ」と称えてはいても、決して批判してはいないのである。