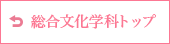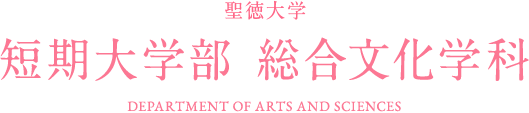(100) 江戸の珍談・奇談(1)
14.02.04
『江戸真砂六十帖広本』から脱獄王の話を一つ。
尾州九右衛門という盗賊の頭があった。日本左衛門に匹敵する大泥棒で、手下五六十人を率い、東海道は言うに及ばず、方々で押し込み強盗を働いていた。ある時、三河の国岡崎で召し捕えられ、牢屋に入れられたが、やすやすとその夜に抜け出す。また浜松の牢に入った折にも抜け出す。忍びの術を心得ていたらしく、並の盗賊ではなかった。
脱獄の圧巻は、相模の国小田原で運が尽きて捕えられた時の方法にある。たまたま将軍が他界した直後であったため、仕置きが延引されていたところ、九右衛門は牢屋の番人に「長々お世話になりました。最期の名残に念仏を唱えたいがよろしいか」と許可を求めた。その分ならば苦しゅうない、勝手にいたせ、と番人が答える。九右衛門が高声に念仏を唱えると大変な上手である。退屈していた番人も声を合せて唱え始めた。
番人たちは、煎り豆などを持参して茶を啜っている。それを九右衛門が所望すると、食べる振りをして豆を隠して貯え、茶を一杯下されと望む。遣わされた湯呑を取り落したふりをして割ってしまう。その欠片を手に入れるためである。
さらに、蚊が多くて難儀するから、蚊帳が一張ほしいと願い出る。番人が目付の許可を得て蚊帳を吊ってやると、蚊帳の陰に隠れて、茶碗の欠片を竹の割れ目に並べて急ごしらえの鋸を作り、牢屋の格子を引き始めた。声高に唱える念仏に合せて引くから、誰も気付かない。そのうちに念仏の声が絶えたので、蚊帳の中を伺うと、もぬけの空である。
小田原では追っ手を派したり、江戸へ飛脚を立てたりと大騒ぎである。ところが、足柄越えの手前で川普請を行なっていた百姓らが怪しい男を捕えたところ、九右衛門であった。長期間牢屋に入っていたため、足が思うように進まなかったのである。
これに懲りた奉行所が、番人を増やし、油断なく警戒したため、九右衛門は遂に獄門に掛かり、刑場の露と消えた。〈中央公論社版『燕石十種』第四巻、87~88ページ〉
江戸時代の牢屋の格子は木枠だったから、比較的切断しやすかったかもしれない。それが、近代以降は鉄格子となり、監視体制も格段に厳しくなった。だが、それをも突破し、生涯に4度の脱獄に成功した猛者が実在した。昭和の脱獄王と呼ばれた白鳥由栄(よしえ)である。
白鳥の脱獄劇については、吉村昭『破獄』(昭和61年、新潮文庫)に詳しい(小説中、白鳥は佐久間清次郎という仮名を用いている)。1936年、独房の合鍵を巧妙な手段で造って青森刑務所を抜け出したのを皮切りに、1942年秋田刑務所、同44年に網走、47年には札幌と、看守や警察を嘲笑うかのように脱獄・逃走している。
脱獄に至る計画性と頭脳の冴えは特別に優れていた。有名な例は、網走刑務所脱獄の方法だろう。食事として与えられる味噌汁を手錠のナットと視察窓の鉄枠に吹きかけ、腐食するのを待つという持久戦を採った。さらに、頭しか通らない孔から脱出するのに、肩の関節を外している。そんな特技ばかりでなく、身体能力は群を抜き、怪力無双であったらしい。
秋田刑務所で収監された鎮静房は、明かり窓が天井についただけの独房で、稲荷房あるいはトーチカ房と呼ばれ、逃走不可能とされていた。にもかかわらず、3.2メートルもある天井まで昇り、その天窓を破って脱出している。道具が一切ないのにどうして昇ることができたか。ぜひ小説に当たっていただきたい。
では、白鳥はなぜこれほど脱獄に執念を燃やしたのか。それは、人間的な扱いを受けなかったこと対するに抵抗だという。自分に対して酷薄に接した看守が当直する日をわざと狙って逃げていることからもそれは窺える。白鳥は、青森刑務所を抜け出た後、以前に小菅刑務所で世話になった看守長を訪れ、自首した。東京拘置所での訊問の際、なぜ小菅へ戻ったのかと尋ねると、「主任さん(=看守長)は、私を人間あつかいしてくれましたから……」と眼を潤ませて言った(『破獄』78ページ)。
ところが、秋田刑務所では規定以上に苛酷な扱いを囚人に施しているという事実はなく、脱獄の動機は、妻子に会いたいという願望以外に看守に対する反感と寒気に対するおそれではないかと検事は推測した。また、小菅刑務所の所員のもとに自首して出たのは、戦局の悪化によって食糧事情が深刻さを増し、三食を約してくれる刑務所に入る方が賢明と思ったとも想像された(同、80ページ)。
白鳥は、札幌刑務所を脱獄して半年後、札幌警察署管内琴似町で身柄を拘束されることになる。警察官が穏やかに煙草を差し出したことをきっかけとして、本人から名乗り出た。小説では、以下のように佐久間に語らせている。
「不審尋問された時、煙草をくれましたのでホロッとし、佐久間だと名乗ったのです。日本刀は持っていましたし、警察の旦那たちは私服で丸腰でしたから、オイッ、コラッ式でやられたら日本刀をふりまわして逃げましたよ。煙草一本で、気持がくじけました」〈『破獄』273ページ〉
札幌から府中刑務所へ移送された佐久間を待っていたのは、脱獄計画など思い浮びそうにない肩すかしの待遇だった。所長の鈴江圭三郎は、まず四貫目もある佐久間の手錠・足錠を鉄鋸で切り外し、独房には花を置いた。囚人たちに競わせて栽培した花である。軽作業を与え、決して抵抗する対象を作らないよう扱っていると、ある日、花びらを掌に乗せて香をかいでいる佐久間の姿を看守が報告する。巡回しながら再び房の前へ行くと、床に落ちていた花びらが一片もない。花びらはどうしたのかという看守の問いに対して、佐久間は口を指差した。口をわずかに動かし、花びらを味わうように舌に乗せていたという(同、331ページ)。
ところで、佐久間(白鳥)をどのように札幌から府中へ護送したか。吉村は、この小説を書くために、鶴羽菊蔵という元札幌刑務所長から聞き取り調査をした。鶴羽氏は、当時網走刑務所の看守長を務め、札幌では戒護課長の職にあった。佐久間の脱獄に二度遭遇するという貴重な体験を持つ最も重要な人物である。刑務所の所員も退官した者も口は極めて重い。受刑者についても出所者についても、プライバシーを徹底して守ることが義務付けられているからである。白鳥を仮名にする、事実を歪めない、白鳥はすでに物故者であるなどの理由から、ようやく体験談を話してくれた(吉村昭『人生の観察』―2014年 河出書房新書、119ページ)。
札幌から府中への護送経過について吉村が「その記録はないのでしょうか」と尋ねると、鶴羽氏は、さあ?と首をかしげた。だが、その表情にはあるらしいと吉村は感じ取る。四度目に訪れた時、「物置にこんなものがありましたが……」と言って、数枚綴りの書類をテーブルに置き、鶴羽氏は庭に出て植木の手入れを始めた。それは、まさしく護送経過を記したものである。ノートに書き取る暇はない。吉村は、低い声でそれを読み、テープレコーダーに収める。しばらくして戻った鶴羽氏は、終始穏やかな眼で雑談をしていた(同書121ページ)。吉村の誠実な人柄と取材態度が齎した成果といっていい。
なお、白鳥は府中刑務所で模範囚となり、1961年に釈放されている。