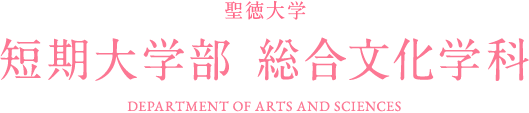(42)『近世畸人伝』―池大雅―(1)
12.06.12
江戸中期の文人画家・書家として高名な池大雅(いけのたいが)―1723~1776―といっても、弱年の読者には馴染みのない名前であろう。実は本稿の筆写とて、何かの図版に載っていた「十便十宜図」(川端康成の蒐集品として知られる)を見た程度であるから、はなはだ心許ない。では、なぜこの人物を取り上げたかというと、その天然自然ともいうべき奇人ぶりに魅力を感じたからである。
伴蒿蹊(ばんこうけい)『近世畸人伝』(寛政2年―1790―刊)によれば、3歳で書を始め、5歳にしてすでに神童の片鱗を見せている。一日万福寺で堂頭千杲(せんがい)禅師を前に大楷書を披露すると、禅師ばかりか同席した僧らも感服し、詩を賦してこれを賞したという。〈『近世畸人伝・続近世畸人伝』―平凡社東洋文庫、154ページ〉
長じて唐風の山水画を学び始めたころ、扇面に描いた絵を携え、近江・美濃・尾張を廻って売ろうとしたものの、初心を怪しみ、誰も買わない。空しく帰洛しようと瀬田の橋を渡る時、その扇をすべて湖水に投じ、これによって竜王を祭ると言った。その後、短時日のうちに書画の名声が広まったという伝説さえ残している。(同、154ページ)
また、大雅が江戸から奥州へ旅をした帰途、禅寺に世話になった。住持の留守にもかかわらず昼飯を供してくれた礼として偈頌(げしょう、悟りの境地を表す漢詩)を書き残して去る。帰った住持がそれを見てひどく感心し、後を追うが、つかまらないまま、とうとう京都まで来てしまう。偈に記された池無名を頼りに探しまわり、祇園の社に掲げられた蘭亭図に同じ署名を見つける。僧坊に駆け込んで作者の居所を知り、ようやく対面することを得た。だが、大雅を探し当てたら、もう京に用はないと踵を返して奥州へ旅立ったという。(同、159ページ)
これでは単なる偉人伝となってしまう。だが、さすがに伴は池大雅の畸人(奇人に同じ)たるゆえんを洩らしはしない。
「多く人の不意に出る話をいはば」と、履歴を述べた前段の退屈を振り払うように奇談を繰り出す。
大雅が江戸に下った時の話である。知人を頼って某大名の屋敷に宿った。6月18日になり、故郷祇園の社で行なわれる神事御輿洗(みこしあらい)の日である。紙で人形を作り、火を着けて邸内を廻ろうとした時、大名の子息がそれを見たいから持ってこいとの使いがある。しかし、囃子に紛らし、聞こえないふりをして廻っている。何度も使いがやって来て催促するので、今参ろうというその時には、すでに人形を焼き尽してしまった。「これはしたり。だが、これは祇園の神に奉る志であるから、他人に見せてほしいとは神が願っていないはずだ。」と言ったところ、大名の怒りに触れて、その邸から追い出されてしまう。本人は、それももっともだと笑って済ませていた。(同、155ページ)
大雅の行為にまったく悪意はない。相手の事情には関心を示さないというだけだ。その人となりがよく知られる逸話を今一つ紹介しよう。
ある時、難波へ出立するのに、筆を携えるのを忘れて出てしまう。妻の玉瀾が気付き、筆を持って走る。建仁寺の前で追いついて渡すと、大雅は筆を大事そうに押し戴き、「どちら様ですか、よく拾って下さいました。」と言って去る。妻もまた一言も言わずに帰った。(同、154ページ)
自分の妻かどうかくらい分りそうなものだが、これでは落語そのものだ。
夫のとぼけぶりに怒りもせず、平然と対応した妻玉瀾もまた文人画で鳴らした女流画家である。夫が三味線でだみ声を発すれば、妻は筝をかき鳴らして応じたという。まさに「琴瑟相和す」を地で行く夫婦であった。