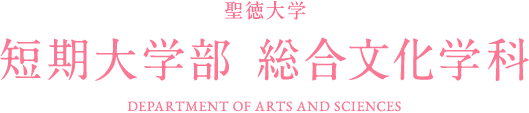(198)江戸の珍談・奇談(26)-4
20.07.27
広島藩最後の藩主浅野長勲(ながこと)公からの直話を録した三田村鳶魚「浅野老公のお話」(『武家の生活』中公文庫、1997年)によると、大名などになるものでないと老公自身が言っていた由。その窮屈さは比類ない。例えば、風呂の浴槽から上がると浴衣を着る。その浴衣は寒暑ともに麻で、いずれも袷一枚である。しかも、帯も紐もない。そのまま居間へ戻ってお召し替えとなる。また、寝間着は、夏は単衣(ひとえ)、その他は袷、綿入れは用いない。これでは寒夜便所へ立つ時、震え上がったろうと想像される(同書18~19ページ)。
いかなる場合にも殿様一人でいることはない。表でも奥でも、雑談は勿論、不用意な言葉があれば、周囲に差し響く。ちょっと脇見をしただけで、御意に入ったことがあったから、誰をご覧になったとか、逆に目障りになったのではないか、という微妙な嫌忌が起こる。殿様は、咳一つするにも斟酌しなければならない(同書23ページ)。
ということは、側付きの家来などはさらに気遣いが必要とされたことになる。江戸城から駕籠で帰り、屋敷の玄関まで来て駕籠を下りると、草履取りが草履を出す。しかし、草履取りは通常殿様に目通りが出来ないことになっているから、投げ草履と称して、遠くから左右ちゃんと揃うように投げるのである(同書56ページ)。
食事も大変だ。浅野家は大名であるが、極めて質素で、朝は焼き味噌に豆腐、昼と晩が一汁二菜だった。殿様は多く食ったり少なく食ったりすることもできない。食い方が減りでもすると、何か調進の仕方が悪いのではないかと、台所奉行が調べることになる。味付けに文句は一切言えない。食物の中にごみが入っていると、人に見せないよう隠すのだが、ある時、鼠の糞が入っていたのを、どうしても隠しおおすことができなかった。そのため大騒動になった。これをそのままにしておくと、責任者が腹を切らなければならなくなるから、特別をもって許すということにした。それも、何か言い草をつけて、止むを得ず入ったのだ、ということにするのである(同書81~82ページ)。
話は遡って江戸開府の頃、会津40万石を領した加藤左馬助嘉明は、南京渡来の焼物の器を多く買い入れていた。その中に「虫食い南京」と呼ばれる十枚揃いの見事な小皿を秘蔵していたが、ある時、客を饗応していた近習の侍がその小皿を一枚割ってしまう。侍が大いに恐れて閑居しようとしている由を聞いた加藤は、直ちに呼び出し、皿を割ったくらいで閑居する必要はないと言って、残りの皿をすべて打ち砕いてしまった。そして、「この皿が九枚残っているうちは、あの一枚は誰が粗相して割ったと、いつまでもお前の粗忽として残ってしまう。それは私の本意ではない。どれほど貴重な器物だとしても、家臣には替えがたい。大体、器物、草木、鳥類などを愛する者は、そのために却って家臣を損なうことが起こるものだ。これは主たる者の心得なければならないことである。珍器奇物はあってもなくても支障はない。家臣は私の四肢である。一日もなくてはならぬものだ。天下国家を治めるのも、家臣があってのゆえだ。」と語ったという(真田増誉『明良洪範』―明治45年、国書刊行会―141ページ)。
『一話一言』には、作者不詳の書「随筆抄」から、この加藤について次の逸話を取り上げてある。
加藤の道具持ちであった弥兵衛という者が、薄禄のゆえに主君の槍の銀を外して換金した。加藤は直ちに厳罰に処することはしない。武士の第一とする槍で、しかも主人から預かった物を盗むからには、何か特別な事情があるに違いないと踏んで、「お前には妻子があるか」と尋ねる。弥兵衛は、母と妻と二人の子に加え甥を三両二人扶持で養っている旨、申し上げた。加藤はこれを聞き届け、薄給の身で六人の生活を成り立たせるのだから、盗みに頼るのも無理はないと罪を許した。さらに、男子を草履取りとして召し出し、娘は奥方へ奉公させ、甥は足軽に取り立てたのである(巻14、308ページ)。
同じ加藤でも虎退治で有名な清正の方は、家来が朋輩の悪口を言った廉で討ち果たされたという事件があった。その際、「以後蔭口を慎むように。ただ気が収まらないというなら、俺の噂を種にしろ。朋輩についてあれこれ言えば喧嘩が絶えなくなる。すると、主人に損をかけて不忠となってしまう。俺のことを言えば、良いにつけ悪いにつけ、自身の戒めとなるからだ。」と家臣を嗜めたという(同上)。
これらの逸話の真偽は定かでないものの、現代の雇用関係にも通じる至言といってよいだろう。(G)