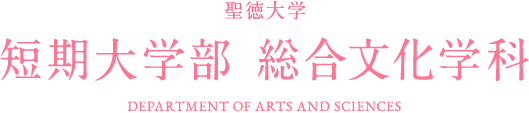(159) 江戸の珍談・奇談(22)-7
16.09.19
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)『怪談』に「十六ざくら」という話がある。
伊予の国和気郡(わけごおり)に、毎年大寒の季節である陰暦1月16日だけに花を開く「十六ざくら」と呼ばれる桜があった。この桜にはある侍の魂が宿っている。すでに100年以上に亙ってこの桜を楽しんできていたが、侍が老年に達したある年の春、突然枯れてしまったのである。悲しむ老侍を慰めるため、周囲の者が桜の若木を庭に植えてくれた。しかし、老木に代わる物はない。老侍は、枯れた木を助けるため、自分が身代わりとなろうと桜の木の下で自害して果てた。その魂が木に乗り移り、再び花を咲かせるようになったのである。〈新潮文庫『小泉八雲集』245~247ページ〉
また、「乳母ざくら」でも、中年に至ってようやく授かった一粒種である娘が15の歳に重篤に陥ると、その乳母が身代わりとなって自分の命と引き換えに娘を救う。この乳母も、所望して庭に植えてもらった桜に命日になると必ず花を咲かせるのである〈同185~187ページ〉。
自分の魂を死後にも永続させたいという死にゆく者の願いと永遠に記憶と伝承に留めたいという遺された者の心情とが合致した時、花木へそれを託すことになった。夏目漱石「夢十夜」第一話も同じ趣向であろう。
以下に紹介する話は、『兎園小説』に収録された奇談中の白眉といってよい。下手な訳文より原文のまま示す。
湯島手代町に岡田弥八郎といひて、御普請方の出方をつとむる人あり。此人のひとり娘、名をせいとよびて、容儀もよく殊に発明なれば、両親のいつくしみふかく、しかも和歌に心をよせ、下谷辺に白蓉斎といふ歌よみの弟子となりて、去年十四歳にて朝がほのうたをよみしが、よくとゝのひたりと師もよろこびける。その歌、
いかならん色にさくかとあくる夜をまつのとぼその朝顔の花
其冬此むすめ、風のこゝちにわづらひしが、つひにはかなく成りにけり。両親のなげきいふべくもあらず。朝夕たゞ此娘の事のみいひくらしゝが、月日はかなくたちて、ことし亥の秋、かの娘の日頃よなれし文庫の中より、朝顔の種出でたり。一色づゝにこれはしぼり、あるはるりなど、娘の手して書き付け置きたるつゝみをみて、母親猶更思ひ出でゝ、かく迄しるし置きたる事なれば、庭にまきて娘のこゝろざしをもはらさんとて、ちいさなる鉢に種を蒔きて、朝夕水そゝぎなどしたるほどに、いつしか葉も出で蔓も出でたれど、花は一りんもさかざりければ、すこし時刻おくれにまきたるゆゑ、花のさかぬ成るべし。されども秋に、秋草のさかぬ事やはとて、さまざまにやしなひしが、さらに花の莟だになし。ある日 父弥八郎は東えい山の御普請場へ出でたるあと、母は娘が事のみわすれかね、朝顔を思ひながら、うつらうつらとねむりたるが、娘の声にて、おかゝさま花がさきましたといふに驚きさめぬ、あまりいぶかしく思ひければ、朝顔のそばへゆきみれば、一りんさき出でたり。いよいよあやしと思ひて、夫弥八郎が帰るを待ちかねて、此よしをもかたり、花をも見せしよし、此はな、昼夜にさきて翌朝までしぼまずしてありとなん。
右は文化十二乙亥年の事なり。花のさきしは翌子年なり。
文政乙酉孟夏朔 文宝堂 しるす
〈『兎園小説』第四集、92ページ〉
心が温まるような佳話である。叢書『日本随筆大成』の編纂に携わった森銑三の並々ならぬ称賛を引いてこの稿を閉じよう(文中「ヘルン」は「ハーン」を指す)。
本叢書第一回の配本中の兎園小説には、文宝堂の「夢の朝顔」などの好短編が収められている。これがまたいかにもヘルン好みというべき可憐な怪談で、誰かこの話を聞かせたら、ヘルン先生は大いに喜んで、一流の文章で書いたであろうに、ついにそのことに及ばなかったのが惜しい。この話を新体詩にした人に沼波瓊音さんがあるが、それも沼波さんの作品としては、特に推称に値するものとまではいい兼ねる。なお別の形式で書いてみる人はいないだろうかといいたくなる。〈森銑三「むだばなし(一)」―『日本随筆大成』第二期第1巻付録―〉