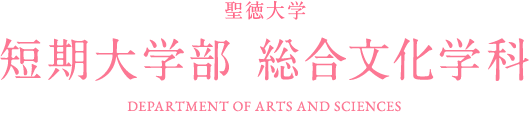(31) 本居宣長(2)
12.02.02
「蛍雪の功」を出したついでに、宣長が槍玉に挙げた、『蒙求』にある「丙吉牛喘(へいきつぎゅうせん)」の話を紹介しよう。
ある春の日に外出した宰相丙吉は、天子が通る道で喧嘩をして死傷者まで出ている情況を見ても、そこを通り過ぎる。続いて、まだ夏でもないのに牛が舌を出して喘ぐ姿を目撃すると、牛の持ち主に牛の様子を詳しく尋ねた。丙吉の行動について部下がその理由を問うと、丙吉は「喧嘩や殺傷事件は長安令や京兆尹の職務である。丞相(=宰相)としては彼らの仕事を評価すればよい。喧嘩のような小事は直接関与することではない。だから無視した。今は春で、さほど暑いはずはないのに牛が喘いでいるのは、陰陽の調和が崩れたためで、異常が起こる徴候だ。陰陽を調和するのが自分の任務であるから、このことについて質問したのだ。」と答えた。部下は彼の答えに畏まって感服したという。
牛が喘いでいるところを宰相丙吉が見かけるところから引用した宣長は、「こはいとをこがましきこと也」と断じた。暑い時分でなくとも、事情によって牛が喘ぐことだってあるだろう。それほど陰陽の調和を言うのなら、常時心にかけていなければならないはずだ。たまたま道すがらこの牛の有様を見て覚ったというのは、いかにもおかしい。もしこの牛の喘ぐ姿を見なかったなら、知らないままだったとでも言うのか、と詰め寄り、「されば、こは、まことに思ひて言へるにはあらで、人にいみじきことに思はせむとての、作り事にこそありけれ。」と斬り込む。そして、すぐさま返す刀で「もしまことにしか心得たらんには、いふかひなき痴(し)れ者なるを、よにいみじきことに記(しる)し伝へたるも、いとをこなり。」と、吐き捨てるように伝記者まで斬り捨ててしまった(八の巻「もろこしの国に丙吉といひし人の事」)。
このように、中国の故事に好んで取り上げられる孝行・勧学・廉直・倹素・廉潔・敏智・果断などを説いた道徳的な訓戒を宣長はまるっきり信用しない。むしろ、ことあるごとにむきになってそれを批判して止まるところを知らないほどだ。果てには「すべて漢国(からくに)などは、よろづの事、実(まこと)はあしきがゆゑに、それをおほひ隠さむとてこそ、さまざまに飾り作るにはありけれ。」(四の巻「世の人かざりにはからるるたとひ」)とまで言い、現在なら国際問題にまで発展しそうな危険な言論を発していた。
さらに宣長の言うところを見よう。上に紹介した丙吉に続いて、『史記』「魯周公世家」にある周公旦の逸話が挙げられている。
周公旦という聖人が、魯国へ赴く子を戒めるのに、「我一タビ沐スルニ三タビ髪ヲ握リ、一タビ飯(めし)クフニ三タビ哺(ほ)ヲ吐(はき)テ、起(たち)テ以テ七ヲ待ツ、猶(なほ)天下ノ賢人ヲ失ハムコトヲ恐ル」(宣長の訓読による)と言った。天下の士が訪れた時には、シャンプーをしている手を三度中断し、一度の食事中に三度飯を吐き出して迎えた。礼を失して天下の賢人を得る機会を逃したくないからだ。お前も魯国に行ったならば、決して驕り高ぶらず、礼を重んぜよと諭したのだった。
これに対しても、「もしまことに然したりけむには、これも世の人にいみじきことに思はせむための、はかりこと也。」(八の巻「周公旦がくひたる飯を吐出して賢人に逢ひたりといへる事」)と宣長は決めつけ、いかに賢人を求めているからといって、口に入れた飯を呑み込む間を待てないはずはない。出迎えに歩きながらでも飲み下すことは簡単だ。それをことさら吐き出して人に見せるとは、とんでもない、と言うのだが、ここまでくると、漢文を習いたての生意気な学生が、未熟な論理を振り回して、些細な難点を鬼の首でも取ったかのように言いふらす稚気さえ感じられよう。宣長が最初に学んだのは儒学である。およそ漢籍に疎いはずはなく、現在の学者だって及びもつかないほどの素養と読解力とを具えていたことは間違いない。
だが、本人はいたって本気なのである。宣長は、このような「漢意(からごころ)」と称する中国思想を批判したばかりではない。仏教思想にまでその矛先は及ぶ。例えば、兼好法師『徒然草』さえも、その例外となることはなかった。
「花は盛りに、月は隈(くま)なきをのみ見るものかは。」(徒然草・137段)という禁欲的な美学を「人の心に逆(さか)ひたる、後の世のさかしら心の、つくり風流(みやび)にして、まことのみやびごころにはあらず。」と指摘する。また、「長くとも、四十(よそぢ)に足らぬ程にて死なんこそ、めやすかるべけれ。」(同・七)を引いて、仏教に諂(へつら)う考えで、言葉ではそう言っても、心の中で誰がそう思うか、と口を尖らしている。
要するに、中国思想も仏教思想も不自然だというのだ。世にある人々は、恋人に逢えぬことを嘆き、心にかなわぬことを悲しみ憂える。早く死ぬことを願わず、命を惜しまない者はない。先生と仰がれる知識人、上人と敬われる法師などが、月や花は賞翫しても、いい女を見て目もくれないで通り過ぎるなんてことが本心から行なわれているとは思えない。このような自然に生まれる心情に逆らって抑圧することは、外国の習慣に迎合したへそ曲りのやることで、虚飾としか言いようがないのだと主張した。これが宣長の思想の根本にあったのである。