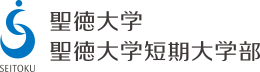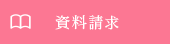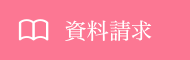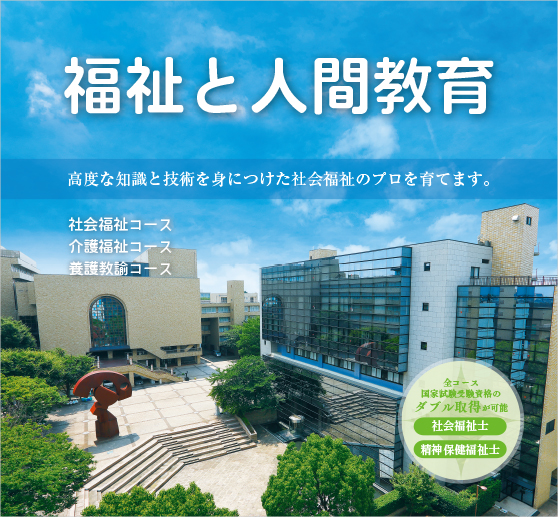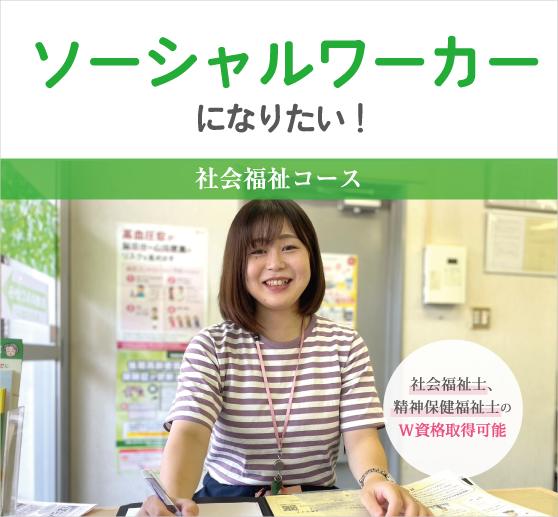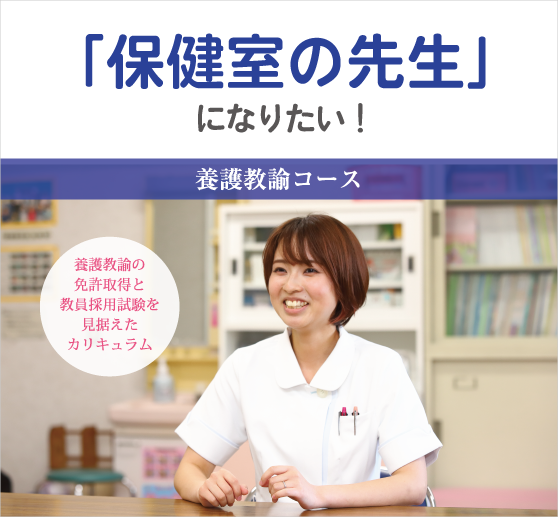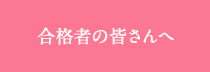看護学科とのフィールドリンケージ授業
26.01.16
1月13日(火)の2限に、1054・1055教室にて学科とのフィールドリンケージ授業を行いました。
これは、看護師を目指す看護学科の学生と社会福祉士を目指す社会福祉学科の学生が合同で、退院して居宅で生活を始める患者の模擬事例を使って支援計画を立てるグループ演習です。
この日までに、それぞれの学科で患者が抱える課題を整理し、それに基づく支援計画を検討してあります。そして、この合同グループ演習で看護師と医療ソーシャルワーカーの役割でお互いの専門性に基づき意見を出し合いながら、一つの支援プランをまとめます。
看護学科は73名、社会福祉学科は32名の3年生が対象で、看護学科4~5名と社会福祉学科2~3名の合同グループを作って課題に取り組みました。十分に時間をかけて事前の準備をしたため、欠席もなく、とても積極的に意見交換ができました。看護学科の参加者からは、「サービスの利用料を視野に入れることは頭になかった」など、ソーシャルワーカーの職務や視点に気づいた感想が。
授業が終わって、「授業の前には緊張したけれど、とても楽しかった!看護学科の学生はとてもフレンドリーで親切だった!」との感想が聞かれました。
社会福祉学科の教育目標にある「個別のニーズに応じたサービス提供」、「他の職種との連携」に通じる第一歩。ソーシャルワーカーの実践力獲得に向けて大きな一歩を踏み出した3年生です。 (報告:横井)