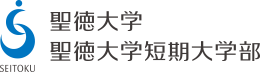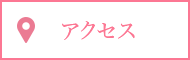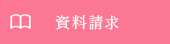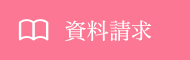教員紹介 教育学

染谷 由之 (教授)
専門・研究分野
学校・学級経営、道徳教育、小学校教育全般
メッセージ
小学校の先生になるためにもっとも大切なことは何でしょう?それは、学力でも体力でもなく、「子供たちのことが大好きだ。」という熱い思いです。子供は、先生が本当に自分のことを大切に思ってくれているかどうかということを、会ったその瞬間につかみます。子供たちとの信頼関係を築き、誰もが楽しいと思えるクラスをつくることができる先生になるために、本学で、皆さんのよさを伸ばし、教師としての魅力を最大限に高めていきましょう。
経歴
東京都公立小学校校長を経て、2020年本学着任。東京都小学校道徳教育研究会会長、東京都道徳教育推進委員会委員長、東京都小学校道徳研究開発委員会委員長、文部科学省 心のノート改訂作業部会協力委員などを務める。現在は日本道徳科教育学会理事、主な著書・論文 「考え・議論する道徳の授業づくり」「主体的・対話的で深い学び」となる道徳科の指導と評価の在り方についての一考察 「総合的な学習の時間における教科等横断的な指導に関する一考察」など

石田 清彦(教授)
専門・研究分野
社会科教育、総合的な学習教育、教育方法、教育政策
メッセージ
時代が変わっても大切にされている「教師の授業の技」と、時代とともに変化する「新しい教育の 方法」を学び、次代の教育を担う教員を目指して、一緒に頑張りましょう。
経歴
千葉大学教育学部卒。千葉県小学校教員、中学校長、義務教育学校長、千葉県市川市教育委員会課長、同市公立学校長会長を経て、令和5年本学に着任。千葉県CSアドバイザー。主な著書「小学校の優れた社会科授業の条件」(共著)。日本社会科教育学会、日本生活科・総合的学習教育学会等の会員

坂本 紀子(教育学科長、教授)
専門・研究分野
近代日本における学校と地域の関係史
メッセージ
主に「教育原理」「教育基礎論」という、教育学の基礎的な授業を担当しています。 教育事象の基礎、基本や、歴史的な過程に視点を向けると、「普通」のこと「当たり前」だ、と思っていたことが、「普通」「当たり前」ではないことに気づきます。教育の基礎、基本を学び、みなさんが抱いている教育観を見つめなおしてみませんか。
経歴
早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。博士(文学)。北海道教育大学教育学部教授を経て、2023年4月に本学に着任。主な著書:『明治前期の小学校と地域社会』(単著)、『近・現代日本教育会史研究』(共著)、『学校と学区の地域教育史』(共著)など。

増井三夫(副学長、教授)
専門・研究分野
教育史 社会思想史 社会哲学
メッセージ
「いかに生きるか」を教育の本質として問うことが大切です。
経歴
筑波大学博士(教育学)、ベルリン自由大学客員研究員、上越教育大学教授・副学長、聖徳大学教授・副学長

太田裕子(教授、特別支援教育コース主任)
専門・研究分野
特別支援教育(視覚障害、発達障害、知的障害、インクルーシブ教育)
メッセージ
特別支援教育は、教育の原点と言われています。 「子どもたち一人一人をしっかりと見つめ、理解し、そのもてる力を最大限に伸ばす。」 このことは、すべての教育につながります。さあ、ご一緒に学びましょう。
経歴
筑波大学大学院教育研究科修了。小学校教員、指導主事、小学校長、ロンドン日本人学校教員を経て、2018年本学に着任。日本特殊教育学会、日本教育心理学会、日本LD学会、日本臨床発達心理士会会員。学校心理士、臨床発達心理士、特別支援教育士スーパーバイザー。特別支援学校学習指導要領改善の執筆に係る調査研究協力者(平成10~11、平成18~21)。中央教育審議会専門委員(平成23~25年)。 主な著書 学校でのICT利用による読み書き支援(共著)、障害者教育・福祉の先駆者たち(共著)、ロービジョンケアの実際(共著)など

川並芳純(教授)
専門・研究分野
児童教育学
メッセージ
大学には、ヒトやモノ、豊かな資源がたくさんあります。知識と経験豊富な先生方、優しい先輩、宝の山のような図書館をはじめとした施設・設備。先輩の皆さんはそれらを上手に自分の糧として、これまでの実績を積み上げてきました。受験生の皆さんも、この聖徳でしっかりと知識と技術を身につけることができると思います。
経歴
慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程単位取得満期退学。教育学修士。聖徳大学附属女子中学校高等学校校長、聖徳大学附属取手聖徳女子中学校高等学校校長、聖徳大学附属小学校主事兼務。

河村久(教授)
専門・研究分野
特別支援教育、知的障害教育、肢体不自由教育
メッセージ
特別支援教育は、今やすべての子どもの教育を目指す学生にとって必須の専門性の一つとなっています。幼稚園や小学校等の通常の学級の教員を目指す人も、ぜひ一緒に学びましょう。
経歴
横浜国立大学教育学部卒。東京都養護学校及び小学校教員、指導主事、小学校長等を経て2008年本学に着任。日本特殊教育学会、日本LD学会会員。特別支援教育士スーパーアドバイザー。主な著書『小1担任の全仕事』(編著)、『つまづきのある子の学習支援と学級経営』(共編著)など。

腰川一惠(学長補佐、教職研究科長、教授)
専門・研究分野
特別支援教育の学校(園)内支援体制
メッセージ
教育や保育の場では、特別なニーズのある子どもたちが過ごすことが普通なことになっています。一人ひとりに適切なかかわりや配慮がわかる保育者、教育者になってください。
経歴
筑波大学大学院心身障害学研究科博士課程修了。博士(教育学)[筑波大学] 知的障害養護学校教諭を経て、2005年本学に着任。発達障害学会評議員、発達障害 システム学会評議員。主な著書『ダウン症ハンドブック』(共著)、 『気になる子の保育実例集』(監修)など。

金琄淑(准教授)
専門・研究分野
教育課程論、小学校英語カリキュラムの評価研究
メッセージ
主に経験されたカリキュラムに興味を持っています。みなさんが学校教育を通して経験したものが、どのような教育的な価値があるのかを卒業生への調査を行い検証しています。研究分野は、カリキュラム評価、国際化に対応した小学校英語カリキュラム開発、小学校英語教員養成・研修カリキュラム開発などです。大学生活を通して経験値を高めてください。
経歴
筑波大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学 主著/主論文:『学校教育のカリキュラムと方法』(共著、協同出版、2013) 「日本と韓国の小学校教員の英語学習認識度に関する実証的研究」(『JASTE研究紀要』日本児童英語教育学会、第34号、2015)など

山崎奈々絵(教授、小学校教員養成コース主任)
専門・研究分野
教師論、戦後日本教育史
メッセージ
主に教師が育成される仕組みやどのように成長するのかを歴史的に研究しています。歴史を知ることで、現代やこれからの教師・教育のあり方を幅広く、また深く考えることができるようになります。ぜひ幅広い視野から教育について学んでいきましょう。
経歴
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程単位取得満期退学、博士(社会科学)、東海大学助教を経て2014年本学に着任。主な著書『戦後教員養成改革と「教養教育」』(単著)、『新・教職入門』(共著)、『青山学院女子短期大学六十五年史通史編』(共著)など。

北畑彩子(講師)
専門・研究分野
障害者教育の歴史、インクルーシブ社会の形成
メッセージ
日本と海外の障害者教育の歴史について研究を進めています。特別な支援を必要とする子は毎年増え、必要な支援の内容も多様化しています。日本にも海外にも、教育の対象者を徐々に広げ、教育を充実させるために奮闘してきた歴史があります。そうした事例を学びながら、日本の特別支援教育の未来を共に考えてみませんか。
経歴
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(障害科学)。 公的機関での障害者の就労支援の職を経て、2016年本学に着任。主な論文「20世紀後半カナダにおける障害当事者・支援者による権利運動の展開-雇用問題に着目して-」(2021年、博士論文)、「カナダ・オンタリオ州における知的障害児の教育保障」(2018年、学内研究紀要)など。