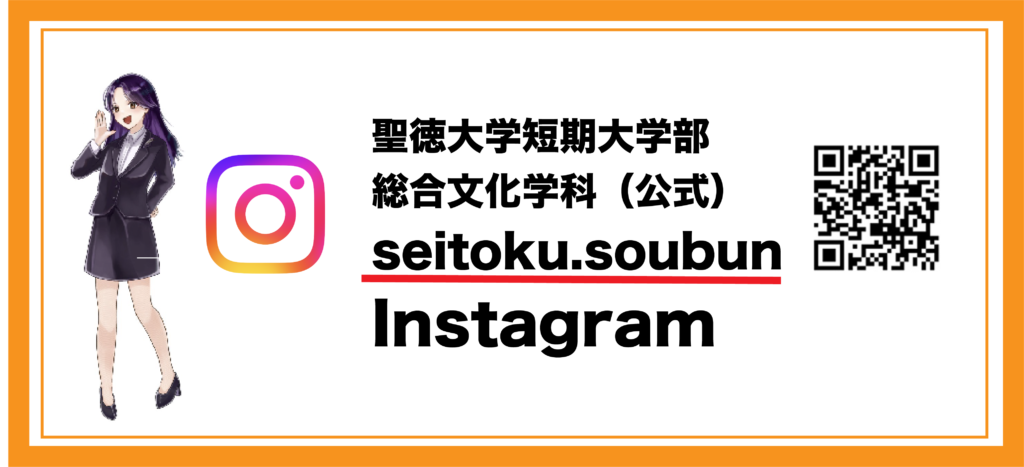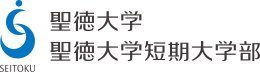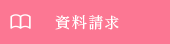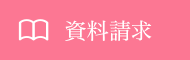【授業紹介】基礎調理実習
25.04.30
ブログをご覧の皆さん、こんにちは。
4月も今日で終わりですね。新1年生も、少しずつ学生生活に慣れてきたようです。
さて、フードマネジメントコースの1年生の授業では、「基礎調理実習」があります。
まさに〝調理の基礎”を学ぶ授業です。
これまで、まな板の置き方、まな板の前に立つ姿勢、包丁の持ち方、野菜の切り方、調味料の計量方法等、料理を学ぶ上での基礎的なことを学びました。
そして第3回の先日は、和食の要である「出汁」を中心に、材料、引き方、料理について学習しました。

本学の実習で使用する出汁の素材は「鰹節」と「昆布」です。
水の中にさっと洗った昆布を加えてから火にかけ、小さい泡がたくさん出てきたら昆布を静かに取り出し、一度沸かしてから鰹節を加えて火を消し、1分ほどしたら濾します。
「なぜ、昆布を先に取り出すのか」、「なぜ鰹節に入れる前に一度沸騰させるのか」など、理由を説明しながら授業は進みます。
ご存じの方も多いかと思いますが、昆布に多く含まれているうま味成分は「グルタミン酸」、鰹節に多く含まれているうまい成分は「イノシン酸」です。
通常、1+1=2となりますが、イノシン酸とグルタミ酸を合わせると、うま味が6~7倍にもなりことが科学的にも証明されています。これを「相乗効果」と呼びます。素材それぞれでも出汁は取れますが、合わせたほうがずっと、うま味を強く感じることができるわけです。
このうま味を活かし、肉豆腐とかきたま汁を作りました。実習室内には、出汁の豊かな香りが広がりました。うま味を効かせることで、薄味でも満足ができ、減塩効果も期待できますね!
また今回は、旬のグリンピースを加え、文化鍋でご飯も炊きました!(^^)!。

来週はお魚をおろします!
インスタでも発信していきますので、宜しければご覧ください!