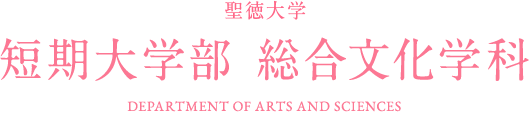(86) 三遊亭圓朝『怪談 牡丹燈籠』(4)
13.09.15
明治9年-1872-、圓朝38歳の時に本所二葉町に越した。小島の小説によれば、一子朝太郎を生んだお里と別れた後、ここで父円太郎の妾であったおやいと結婚することになっている。永井啓夫『三遊亭円朝』(昭和37年、青蛙房)には、本文中にも年譜にもおやいの名は見えない。永井によれば、朝太郎誕生の翌年にお幸という女性を迎えているから、もし架空でなければ、おやいは正室ではなかったということになろう。『牡丹燈籠』のプロットは、そのおやいからヒントを得たという。その話自体は奥野も指摘しているが、小島の小説とはやや異なる。奥野の要約をまず示そう。深川北川町の米問屋飯島喜左衛門の家庭の事情だという。
喜左衛門の次男弁次郎は、八幡境内の茶の宗匠のもとにおいて材木問屋の娘お露と相知り、やがてこれと結婚するにいたったが、お露は病弱のためまもなく死去した。たまたまお露に妹があり、これが姉の跡に直ることに話がきまって、いよいよ婚礼という晩、その花嫁たる妹が急死するという不祥事がおこったので、弁次郎は厭世的になり上野池の端に隠棲した。ところがここにお露と妹の二人の亡霊が現れるという怪談が流布されはじめた。その後弁次郎は剃髪して僧侶になった。(岩波文庫解説、183ページ)
病弱の姉が夫の世話のできないのを見かねて、妹のおはるが世話を見に来た。病人が看護婦に惚れるような心持ちが弁次郎の胸に動き、おはるもまた美男の弁次郎に思いを寄せて行く。神経が特別に鋭くなっている病人には、人目を避けて逢瀬を重ねる二人の行動が手に取るように悟られた。2年を経て亡くなったお露の一周忌が済むと、おはるを後添えにという話が持ち上がる。いよいよ、婚礼の式も終わり、お床入りという段になって、おはるは突然虚空をつかんでうしろへのけぞったと思うと、息が絶えた。小島の小説中でおやいが語る話ではこうなっている。
永井によれば、『牡丹燈籠』の原案の出来上がったのが、圓朝の23歳ごろとされている。それが正しいとすると、朝太郎の生れるのが、その7年後の慶応4年-1868-だから、おやいからヒントを得たという小島の話と合わない。
小島の祖父利八(りはち)は、圓朝と同じ寺子屋に通った幼馴染で、後年まで昵懇の仲であったという。その利八から聴取し、また自身も高座に通って圓朝を直接耳にしたものだから、一方ならぬ思い入れがあろう。各方面に取材を重ねたと本文中にも見えはするものの、どうしても圓朝寄りの同情溢れる書き方になってしまうのは仕方があるまい。